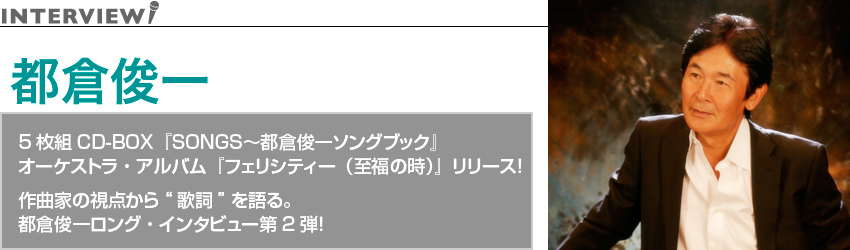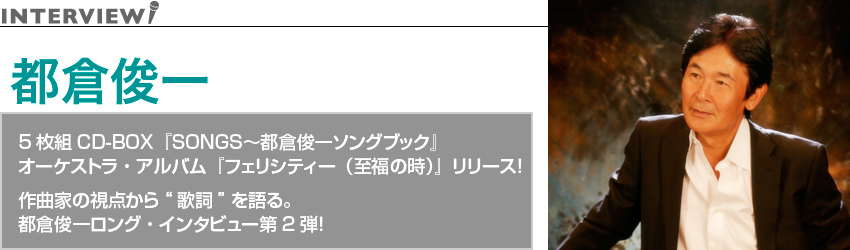都倉先生ご本人をお迎えしてのロング・インタビュー第2弾。数多くの新人をプロデュースしてきた都倉先生に“勝手が違った”と言わしめた山口百恵。今なお多くの人を虜にする彼女の魅力を引き出したのは誰だったのか。後半は、作曲家の視点から見た阿久悠作品の魅力について。興味深いお話が続きます。

──都倉先生も阿久先生も、新人アーティストを手がけられる事が多かったですよね。
都倉:僕も阿久さんも、既に大スターとなっていた人にはあまり曲を提供していないんですよね。阿久さんには阿久さんの理由があったんだと思うんだけど。大スターというのは既に自分の世界を持っているから、新たな世界観を持ち込もうとしても、それまでの路線から大きく外れる事に躊躇して、結局、中途半端なものになってしまったりするんですよ。だから、依頼があっても僕は書かなかった。僕はね、ゼロからやりたいですよね。阿久さんとのコンビでも、“スター誕生!”出身の新人歌手をたくさん手がけてきました。でも、山口百恵だけは勝手が違いましたね。
 ──山口百恵さんといえば、デビュー曲「としごろ」と2曲目の「青い果実」以降は全く異なる印象になりましたよね。 ──山口百恵さんといえば、デビュー曲「としごろ」と2曲目の「青い果実」以降は全く異なる印象になりましたよね。
都倉:普通はね、我々が作った世界を歌手に演じてもらうんですよ。1曲ごとにドラマを作って、それを演じてもらう。山口百恵の場合もデビューの時はそれをやった。でもね、なんか違うんですよ。しっくり来ない。ドラマのディレクターも映画の監督もみんな同じことを言う。彼女を演出しようとするとうまくいなかい。本人も一生懸命やっているんだけど、何か違うって。演技をつけるより、彼女が自然に振舞っている時の方がいいって言う。彼女は最初から強烈な自分の世界を持っていたんですね。稀有なパーソナリティを持っている人だった。我々が彼女をプロデュースするのではなくて、我々の方が彼女のテリトリーに入っていってやる。そうするとスゴイことになる。それに気がついたのが「ひと夏の経験」です。
──ある意味、セルフ・プロデュースですね?
都倉:そうですね。山口百恵の本当の魅力を探し出したのは、山口百恵本人ですね。彼女が持つ引力というか求心力というのは、とにかく凄かったですね。僕や阿久さんもそうでしたけど、彼女と仕事をした人は、ドラマのディレクターも映画監督もみんな百恵ファンになっちゃう。篠山紀信さんもそうだった。我々が彼女に舞台を与えるのではなく、我々の方が彼女に世界に入っていく。そうすると彼女がいちばん輝くわけ。引退する時の潔さを見ればわかると思うけど、自分の信念がハッキリしててね、軸が全然ブレない人でしたね。

──作詞家、作曲家が歌い手側に惹き込まれるということもあるわけですね。
都倉:そうですね。例えば、沢田研二なんかはその典型かもしれないですね。「時の過ぎゆくままに」(75年)から、阿久さんが沢田研二の詞を書くようになって、「勝手にしやがれ」をはじめ一連の作品を、僕は第三者的にずっと見てたけれど、あれは、沢田研二主導で進んでいる印象でしたね。
──沢田研二の魅力を引き出したのは、沢田研二自身だと?
都倉:あの時代に、化粧してヒカリモノつけて。非常に妖艶で色っぽくて、今で言うヴィジュアル系の原点みたいなものでしょう。でもあれは、沢田研二自身が生み出した世界。沢田研二が自分で変わりたかったんだ。だから、「勝手にしやがれ」で帽子飛ばしても、「カサブランカ・ダンディー」で♪ボーギーボーギーってやっても、軸は全然ブレなかった。ああいう色っぽさというのは、誰もが出せるものではないですからね。

──沢田研二さんと並行して、ピンク・レディーの一連のヒットがあるわけですが、ピンクレディの楽曲も、1曲ごとにドラマがありましたね。
都倉:「UFO」や「透明人間」なんかは言ってみればSFですしね。ピンク・レディーに限らず、SF、サスペンス、コミカルなものからグロテスクなものまで、あらゆるジャンルのフィクションを書ける作詞家と言ったら、これはもう阿久さん以外にはいないでしょうね。 恋愛ものでも、青春小説っぽいものもあれば、大人のエロティックな世界まで、ほんとに幅広かったですからね。そして、阿久さんの作品というのは、詞の中に自分が全く介在しない。完璧なフィクション。プロの作詞家というのは、フィクションでストーリーを作るわけだけれども、自分の体験を基に物語を書く人も多いんですよ。でも、阿久さんだけは、完璧なフィクションでしたね。 恋愛ものでも、青春小説っぽいものもあれば、大人のエロティックな世界まで、ほんとに幅広かったですからね。そして、阿久さんの作品というのは、詞の中に自分が全く介在しない。完璧なフィクション。プロの作詞家というのは、フィクションでストーリーを作るわけだけれども、自分の体験を基に物語を書く人も多いんですよ。でも、阿久さんだけは、完璧なフィクションでしたね。
──阿久先生は、どんな風に発想されていたと思われますか?
都倉:一言で言うと“目のつけどころ”ということでしょうね。ものすごい情報量。世の中の動きを常に捉えている。阿久さんは大のテレビ好きでね。読書量も大変なものだったけれども、なんてったってテレビ好き。朝から晩までずーっとテレビを観てる。それで、入ってくる情報が常に頭の中で整理整頓されてるんだよね。そして、その時々に応じて、膨大なデータの中から、彼が独特に感じたその時代の瞬間風速みたいなものを切り出してくる。ピンク・レディーで言えば「サウスポー」ね。あれは、ワンちゃん(王貞治)の756号(ホームラン世界記録)がもうすぐ出せそうだ、いつだろう、いつだろうって日本中が固唾を呑んで見守っている時に、そうかコレだ!とアイデアが出てくる。野球がテーマなんじゃなくて、王貞治がテーマ。詞のどこにもに王貞治という名前は出てこないし、世界記録の事も出てこない。しかも、その王貞治と女の子が対決するという、空想小説みたいな手法。あれは、あのタイミングでなければ使わなかったと思いますね。そういう時代の読みみたいなものを自分のデータの中からポーンと投げつけてくるんですね。膨大なるデータとその中から何を選ぶかという取捨選択眼。その両方を持っていた人ですよ。

──作曲家の視点で歌詞をご覧になって、お感じになる事はありますか?
都倉:作詞家と作曲家というのは、競い合って、切磋琢磨して、“この歌はメロディで売ってやろう”とか“詞で売ってやろう”とか勝負し合って、そうやって補完関係で作品を高めていくものだと思いますね。だから、やっぱり、詩心のない作曲家もダメだし、曲心のない作詞家もダメだと思う。どんなに言葉が巧みな達人でも、曲心がないとね。例えば、阿久さんなんかね、彼の詞には、言葉のリズムを感じるんですよ。心の中には絶対に曲心というのは持ってたと思いますね。
──リズムという点では、歌詞先行と曲先行とでは大きく異なりますよね?
都倉:僕や阿久さんよりも前の時代というのは、曲先行なんてあり得ない時代だったんですね。必ず詞先行。基本的には、四行詩か六行詩だよね。例えば、四行詩だと16小節で完結しちゃうわけですから、メロディを作るにも限界があるんですよ。曲先行でやるようになって、詞もすごく変わったと思います。例えば、「津軽海峡冬景色」は、演歌ですけど曲先行なんですよ。作曲は三木たかしさんだけど、あの♪タタタ、タタタ、タタタタタタ・・・っていう三連音符のメロディがあったからこそ、阿久さんのあの歌詞が出てきた。あのメロディ、あのリズムがなかったら、あの詞は生まれなかったと思いますね。でもね、あれは、詞だけを読んでも素晴らしいですよ。詞と曲が見事にハマった、いやハメたなってほんとに感心しますね。
──男性作詞家と女性作詞家の違いなどもあるものでしょうか?
都倉:女性独特の言葉選び、オシャレ感というのはあると思いますね。例えば、桑江知子が歌った「私のハートはストップモーション」は、滝真知子さんの詞なんだけれど、当時、桑江知子にこの曲のレッスンをしていた時には、詞の意味までは深く掘り下げてなかったんですよね。それが、今回、『フェリシティー(至福の時)』というアルバムを制作して、僕自身が歌ってみて、色んな事に気づいたんですね。マンションのエレベーターを降りた瞬間に、出会い頭に一目惚れをしてしまうという詞なんだけれど、なぜあれがマンションだったのかって。ああそうか、当時はマンションに住むことがオシャレだったんだとかね。背景があるわけですよ。ああいう発想はね、男には出てこない。春風が吹いたようにハッとときめくというような表現とかね。女性ならではのニュアンスというのはありますよね。

──『SONGS〜都倉俊一ソングブック』は大変幅広い収録となっていますが、特に思い出深い曲、エピソードなどはありますか。
 都倉:大きなヒットには至らず残念だったけれど、フラッシュの「電光石火」は、僕自身とっても気に入っている曲ですね。フラッシュというのは、男の子3人組の歌って踊るグループで、カッコ良かったし、曲も良かったんだけど、ヒットというのは色々なタイミングがありますからね。「ブルーロマンス薬局(ファーマシー)」なんかは、小さなミュージカルでしたね。ポップコーンという“スター誕生!”出身の兄妹デュオのデビュー曲だったんだけど、あの歌詞はね、林春生というフジテレビのディレクターだった人が書いたんですよ。彼はミュージカルが大好きな人でね。恋の病気を治してくれる薬局が舞台で、派手な振付でね、まさに小さなミュージカルでしたね。 都倉:大きなヒットには至らず残念だったけれど、フラッシュの「電光石火」は、僕自身とっても気に入っている曲ですね。フラッシュというのは、男の子3人組の歌って踊るグループで、カッコ良かったし、曲も良かったんだけど、ヒットというのは色々なタイミングがありますからね。「ブルーロマンス薬局(ファーマシー)」なんかは、小さなミュージカルでしたね。ポップコーンという“スター誕生!”出身の兄妹デュオのデビュー曲だったんだけど、あの歌詞はね、林春生というフジテレビのディレクターだった人が書いたんですよ。彼はミュージカルが大好きな人でね。恋の病気を治してくれる薬局が舞台で、派手な振付でね、まさに小さなミュージカルでしたね。
──未発表曲も収録されていますね。
都倉:カプチーノというのは81年にデビューしたバンドで、リード・ボーカルは抜群に歌がうまい女の子でね。僕も張り切って曲を書いて『CITY物語』というアルバムを制作したんだけれど、これがなぜか発売されなかった。何か事情があったんでしょうね。それで、作品だけが残ってしまった。僕としては、すっごく気に入っていた作品で愛着もあったから、今回こういう形でリリースできたのはうれしい事ですね。
──1つの作品集としては、いかがですか?
都倉:今回のBOXは、非常に客観的な作品集になったと思います。例えば、ピンクレ・ディーにしても今回は3曲収録していますが、どういう曲が選ばれるのかというのはとても興味深かったですしね。自分が手がけた作品を第三者的に聴く事で、改めて楽曲の良さに気づいたり、歌詞の奥深さに気づいたり、新たな発見というのもありました。僕にとっても新鮮で有意義な作品集ができたと、とてもうれしく思っています。


|