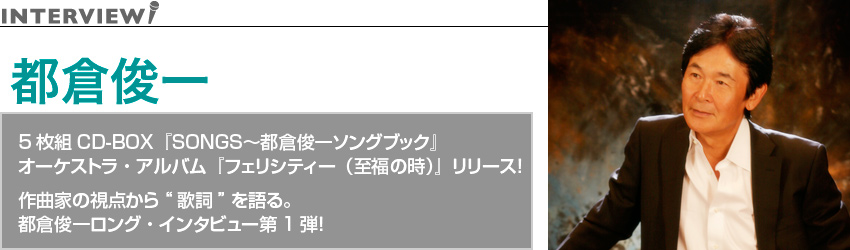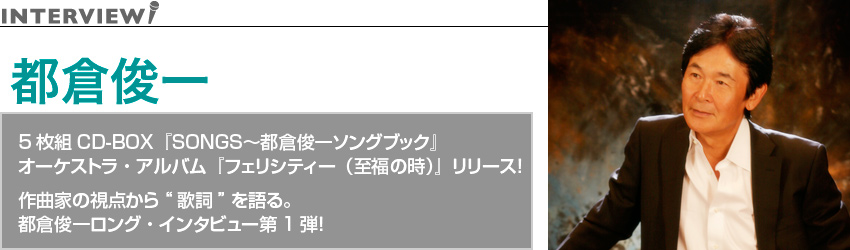作詞家・阿久悠とのコンビで、1曲ごとに歌い手にドラマを与える作風でシンガーを総合的にプロデュース。日本歌謡界を牽引してきた作曲家・都倉俊一の40年に及ぶ活動の集大成とも言える初の本格的アンソロジー『SONGS〜都倉俊一ソングブック』がリリースに。自身の楽曲をアレンジしたオーケストラ・アルバム『フェリシティー(至福の時)』も同時リリース。
都倉作品への新たな注目が高まるなか、都倉先生ご本人をお迎えしてのロング・インタビュー。第1弾は、可憐なアイドル歌手だった山本リンダに強烈な個性を与え大変身させた「どうにもとまらない」をはじめ、作詞家・作曲家がプロデューサー業を兼ねていた70年代の音楽シーンについて、興味深いお話をたっぷりお聞かせいただきました。

──作曲家としてデビューされてから40年。これまでに、何曲くらいお書きになったのですか?
都倉:自分でも把握しきれていないんですよ。CMソングやミュージカルなどもあるからね。JASRAC(日本音楽著作権協会)に登録されている作品だけで、千数百曲あるらしいんだけど、その2倍以上は書いてますね。
──と言うことは、世に出なかった作品というのもたくさんある?
都倉:レコーディングしたけれど発売されなかった作品、あるいはレコーディングにまで至らなかった作品というのはたくさんありますよ。阿久悠さんと僕とで書いた作品だけでも、発表していない曲が何百曲あるかわからない。もったいない話なんだけど、お互いに気に入らなかったり、途中でそのプロジェクトが中止になってしまったりね。70年代の初め頃は、僕も阿久さんもまだそれほど忙しくはなかったから、いい意味での“ムダ書き”をたくさんしましたよ。
──ご自身の作品は、すべて覚えていらっしゃいますか?
都倉:これがね、意外と覚えてないもんなんですよ。我々の仕事というのは、録音してミックスダウンして工場に行くまでは一生懸命やるんだけど、終わったら意外とすぐに忘れちゃう。実は、できあがったレコードは一度も聴いたことがないんですよ。
──では、『SONGS〜都倉俊一ソングブック』で改めてご自身の楽曲に触れてみて、いかがでしたか?
都倉:今回の選曲に関しては、客観的な視点がほしかったからスタッフにお任せしたんだけど、ラインナップを見てね、“こういう曲を選んでくるのか”って興味深かったですね。僕自身が完全に忘れてしまっていた曲もあって、“ああ、いい曲だなぁ”なんて他人事みたいに感心しちゃったり(笑)。とっても楽しかったですね。
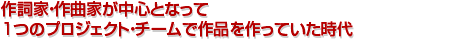
──当時の歌謡曲というのは、ミュージカル的と言うか、俳優が役を演じるように、歌手の方が1曲ごとにその歌の主人公を演じているようなドラマがありますよね。
都倉:その通りだね。例えば、僕と阿久さんは、コンビでたくさんの歌を作ってきたけれど、いつも、阿久さんと言っていたのは、歌手に“小さなドラマ”を与えようということ。歌い手に、毎回、毎回、どんなドラマを与えるか。それが、作詞家・作曲家の役割でもあったんですね。
──当時は作詞家・作曲家がプロデューサーの役割も果たしていたわけですね。
都倉:当時は“プロデューサー”という役職はなかったですけどね。でも、作詞家も作詞家も、今で言うプロデューサーの仕事をみんなしてましたよね。しかも、その部分はタダ働き。サービス残業みたいなものでしたよ(笑)。
──楽曲作りはどんな風に?
都倉:曲が先か、詞が先かというのは、その時々で色々あってね。例えば、阿久さんが引き受けた仕事で、阿久さんが僕に曲を依頼してくる場合は阿久さん主導、反対に僕が阿久さんに詞を依頼する場合は僕が主導。そのプロジェクトの主導者が、今で言うプロデューサーの役割を果たしていたという感じでしたね。
作詞・作曲家だけでなく、当時はレコード会社やテレビ局の中にも、個性の強い名物ディレクターがいてね。そういうディレクター主導で作品を作る事も少なくなかった。例えば、東芝EMIにいらした渋谷森久さん。素晴らしい才能をお持ちの方でね、越路吹雪、加山雄三からドリフターズまで手がけて、劇団四季の音楽監督までなさった方だけれども、彼なんかはものすごい企画力があってね、我々にお呼びがかかるんだけど、思いも寄らない企画が次々出てくるわけ。そのアイデアを我々が楽曲という形にして、そこに歌い手というプロが参加する。そういうプロ集団のプロジェクトでね、1つの作品を作り上げる。そういう作り方をしてましたね。

 ──そういう意味では、総合プロデュース第1弾アーティストは山本リンダさんということになりますか。 ──そういう意味では、総合プロデュース第1弾アーティストは山本リンダさんということになりますか。
都倉:そう言っていいでしょうね。あれは、テレビ局のディレクターから僕が頼まれたんですよ。引き受けようと思ったのはね、そのディレクターが、テレビであの子を作りたいと言ってきたから。テレビというのは、何よりもまず、ビジュアルがあるわけでしょう。それで面白いと思ったのね。リンダ自身も、可愛い子ちゃんのアイドル歌手を卒業したものの低迷している時期で“何でもやります!もう、どうにでもしてください!”という姿勢だったから、自由な発想ができました。
──最初にどんな事をイメージされたんですか?
都倉:僕はね、リンダを絶対にイイ女にしたいと思ったんだ。どんな事をしても。だって、実際イイ女なんだよ。当時まだ22〜3歳でね、スタイルは抜群だしね。そのイイ女を、ただのイイ女じゃなくて強烈な個性を持ったイイ女にしたいと思った。僕の中には、もう絵(テレビの映像イメージ)が浮かんでてね、それで、イントロがあって、メロディがあって、サビがあって、ああしよう、こうしようというアイデアが猛烈に出てきて、スコアを書いた。
──それが「どうにもとまらない」?
都倉:そう。最初からサンバのリズムでいこうと考えていてね、サンバロックみたいなものをやりたいと。それで、イントロからアレンジまで完成した曲を阿久さんに渡して、歌詞を書いてもらった。そしたら、「恋のカーニバル」というタイトルの詞ができてきた。
──最初は「恋のカーニバル」というタイトルだったんですか?
都倉:そうなんだ。なぜならば、サンバだったから。あまり面白くないタイトルだよね。でも、「恋のカーニバル」としてレコーディングしたんですよ。だけど、録音が終わったら、その場にいる誰もがね、鼻歌で♪どうにもとまらない〜って歌ってる。スタッフも含めて全員がね、♪どうにもとまらない〜を連呼してる。誰も「恋のカーニバル」とは言わないんですよ。それで、誰が言い出したのかは忘れましたけど、♪どうにもとまらない〜を、そのままタイトルにしちゃおうって。
──衣装も振付も強烈なインパクトでしたよね。
都倉:1つの作品を作り上げるというのは、作詞家・作曲家がメインにはなるけれども、それだけじゃないんですよね。その他に、衣装があって、振付があって、そういうヴィジュアルも含めてプロジェクト・チームとして作っていく。僕はデザイナーに、色っぽくできるならいくらでも色っぽくしてくれって言ったんですよ。そしたら、あの斬新なデザインが上がってきた。ホントに彼女の特長をよく捉えたデザインだったと思いますよ。振付も素晴らしかった。
テレビの歌番組の演出も、当時は凝ってましたからね。例えば、“夜のヒットスタジオ”なんかでも、ディレクターを呼んでみんなで相談して、こういうイントロで始めるんだけど、こういう絵を撮ってくれない?って、そういう所まで作詞家・作曲家がやってました。まさにミュージカル的な作り方なんですよね。ミュージカルの演出をテレビでやっているような感覚でね。
──70年代になってテレビは欠かせない要素となった?
都倉:70年代を境に、それ以前とそれ以降で何が違うかと言うと、テレビ…映像があるということですよね。ヴィジュアルというのが音楽を大きく変えたと思いますね。僕は、全曲、絵を意識して書いてきた。そういう意味では、僕はとてもいい時代にいたなとも思います。

──時代の変化ということをお感じになりますか?
都倉:70年代後半から、シンガーソングライターの時代になって、松任谷由実(荒井由実)が出てきた。彼女のように、あれだけの個性と独自の世界を持っていれば、それでアーティストとして完結するわけですよね。独特の世界を持っていながら、守備範囲がすごく広い。だから、大衆とリレイトできる。共有できる。非常に稀有な存在ですよね。そういう意味でのアーティストと言えば、桑田佳祐がダントツかな。谷村新司や小田和正もそうですね。独特の世界を持っている、ある種のカリスマですよね。だからと言って、誰もが自作・自演をすればよい言うのは大きな間違いだと思いますね。
──最近では自作・自演が主流になっていますが。
都倉:日本語の歌というのは、1音に1つのシラブル(1音節)しか乗せられないから、非常に言葉数が少なくなる。作詞家というのは、その限られた文字数の中で、どういう言葉を選ぶか、どういう表現をするか、そこに命をかけてきたわけですよ。野口雨情の時代から、西条八十もサトウハチローもみんな、そういう日本語の特色をどうやって生かすか、それを研究してきたんですよね。言葉数が少ない分、行間の意味が非常に大きいというのも日本語詞の特性ですよね。その行間に音が入る事で意味が加わる。作曲家は、行間に意味をつけなければいけない。そうやって、日本の作詞家・作曲家は、日本語の歌を作るという事に挑戦してきたんですよ。だから、自分の言葉をそのままメロディに乗せたたら歌ができると考えるのは大きな間違い。そんな気安いものではないんです。

──うたまっぷには、自作歌詞の投稿コーナーもあり、作詞家を目指しているユーザーも多いのですが、作詞家に求められるものとは何でしょうか?
都倉:例えばね、ここに17歳のアイドルの女の子がいたとして、“私、自分で詞を書きたい”と言ってもね、“お前は17歳で、これまで何回男に惚れた事がある、何回失恋した事があるんだ。それでお前、詞が書けるか”って言えるディレクターがいなくなっちゃってるんですよね。みんな私小説になっちゃってる。
──ノンフィクションである事が必ずしも良い詞になるわけではないと?
都倉:そう思いますね。例えば、岩崎宏美の「思秋期」という曲ね。阿久さんが作詞して、作曲は三木たかしさんだけれども、素晴らしい曲ですよ。あの曲のレコーディングの時、岩崎宏美が泣いたっていうんだよね。“私も、こんな気持ちになる時がくるのかしら。自分の将来が楽しみだ”って。そんな風に、未知の世界を歌い手に与えるというのも“詞”の役割だと思うんですよ。そして、それを歌い切ることによって歌い手も成長する。そういう作家と歌い手との関係というのが、作品を高めることにもなるんですよね。作家と歌い手のそうした関係がまた復活するようにならないといけないと思いますね。


|