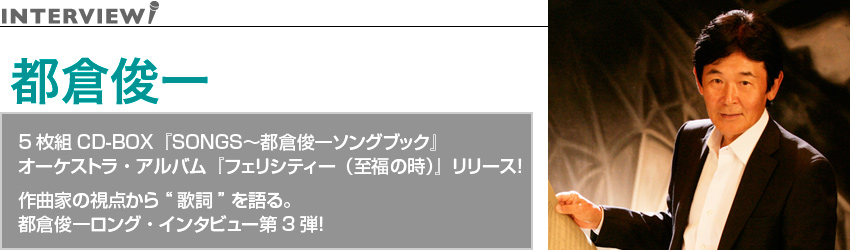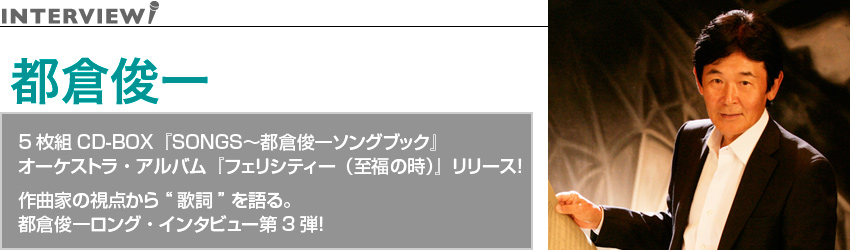都倉先生ご本人をお迎えしてのロング・インタビュー第3弾では、ご自身が率いる“都倉俊一グランド・オーケストラ”のニュー・アルバム『フェリシティー(至福の時)』のお話を中心にお届けします。
「UFO」「ウォンテッド」「どうにもとまらない」などのお馴染みのメロディーが、多彩なオーケストラ・アレンジに。“音楽家としての新たな挑戦”とおっしゃるこの作品にこめられた想いや、ミュージカル作品を通じて再認識したという“詞”の大切さなど、インタビュー第3弾も貴重なお話が続きます。

 ──オーケストラ・アルバムをお作りになろうと思われたのは、何かキッカケがあったのですか? ──オーケストラ・アルバムをお作りになろうと思われたのは、何かキッカケがあったのですか?
都倉:これは、僕がずっとやりたかった事なんです。音の力を試してみたかったんですね。音と言っても、色々な要素があるでしょう。メロディ、アレンジ、そして一つ一つの楽器が持っている音色。言葉を伴わずに“音”が語りかける力というのがどれくらいあるのか、そこに挑戦したいと思ったんです。
──“音”が持つ力を試したいと?
都倉:ええ。例えば、映画音楽の「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」を耳にすると、誰もが思い浮かべるのは、ロバート・デ・ニーロでしょう。多くの人は、スコアを手がけたエンリオ・モリコーネの事は意識しないで、あの曲を聴いている。でも、あの悲しさとか、あのニュアンスというのは、エンリオ・モリコーネの世界なんですよね。映像の添え物ではなくて、音そのものが世界を持っている。
言語や思考など理屈的なものは左脳で、サウンドや映像など情緒的なものは右脳なんてよく言うでしょう。美しいメロディというのは、理屈抜きに人間の情緒を刺激しますよね。ロック・サウンドなんかも同じだと思うんだけど。理屈抜きに音が心を捉えるという事があるでしょう。僕はこれから、音楽家としてね、それを追求していきたいと思っているんです。
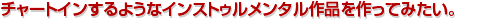
──選曲は、どんな視点で?
都倉:まずは、オーケストラのサウンドにしやすい曲。それから反対に、オーケストラでやった時にものすごく意外性が感じられる曲。例えば「どうにもとまらない」とかね。そういう相反する2つの視点で選曲しています。
──ひとくちにオーケストラ・サウンドといっても、とてもバラエティー豊かなアレンジですよね。
都倉:「UFO」はフルオーケストラで壮大に、「ウォンテッド」はオーケストラだけれどもピアノを中心とした“ピアノ曲”風のアレンジ。「どうにもとまらない」は、原曲はサンバのリズムだったけれど、今回はフラメンコにマリアッチを取り入れた大人っぽいアレンジに。こうしたサウンドだと、かつてのヒット曲も、大人になった世代がいま聴くことができるでしょう。今回、僕が目指したのは、大人が聴けるポップス。日本では、インストゥルメンタル作品の愛好者というのはまだまだ少ないですが、そういう土壌を作っていきたいという思いもありますね。
──確かに、日本では、インストゥルメンタル作品はあまり浸透していないですね。
都倉:日本は“詩”の文化なんですよね。僕が作曲家としての活動を始めて間もない頃、まだ学生だった頃にね、古河政男先生に“都倉くん、音楽(メロディ)は女房だからね。いつも詞を支えるように書かなきゃダメよ”って会う度に言われて、その都度僕は“違います”って言ってきたんだけど(笑)。日本では、作家のクレジットは、作詞・作曲の順番でしょう。作詞が先にくるのは、世界中で日本だけなんですよ。それほど、日本は“詩”=言葉を重んじる文化だという事ですよね。そういう中で、僕は音楽家として、例えば、アンドレ・ギャニオンのように、チャートインするようなインストゥルメンタル作品を作ってみたいという目標を持っています。
──「ジョニィへの伝言」は合唱団によるコーラス、「五番街のマリーへ」や「私のハートはストップモーション」は都倉先生ご自身がヴォーカルをとられていますが。
都倉:そうですね。“声”を使った曲も何曲かありますね。でも、これも、“音”の一つとしての解釈なんですよ。「ジョニィへの伝言」はカナダの混声合唱団が歌っていますが、歌を伝えるとより、言葉を伴う人間の声も、音の要素の一つとして、言ってみれば楽器の一部として捉えているんですね。僕のヴォーカルに関しては、多重録音でソロのボイスは使っていなくて、ミキシングの時も、後ろの方に置いている。そうやって、サウンド全体にステレオ感を出している。言葉の意味は自然と入ってくるわけですから、こうした手法は、音として効いていると思いますよ。
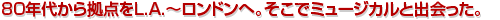
──いずれの曲も、ミュージカルやバレエなど舞台音楽を思わせるアレンジだと感じたのですが、先生がミュージカル作品を手がけられるようになったのは、いつ頃からなのでしょうか。
都倉:1981年に、L.A.に仕事場を移したんですよ。向こうでもレイフ・ギャレットに曲を書いたりはしていましたが、UCLAで学生に戻ったりして、しばらくのんびり過ごしてたんですね。その後、N.Y.に行く機会があって、ブロードウェイを覗いたら、ちょうど“オペラ座の怪人”が上演され始めた頃(N.Y.での初演は88年1月)でね、イギリスからロイド・ウェヴァー(アンドリュー・ロイド=ウェバー)作品が一斉に入ってきて、“ビートルズ以来、第2のブリティッシュ・イノベーション”なんて言われて、一大ムーブメントになっていた。これは面白いと思ってね。88年にロンドンに行く機会があって、ミュージカルに携わるようになって、もうこれが面白くてね、そのまま96年までロンドンに居ついちゃって(笑)。今でもロンドンに事務所はあって、行ったり来たりしていますが、新しいミュージカル・プロジェクトが始まるとロンドンに行きっぱなしになります。
──ミュージカル曲を書かれるようになって、それまでとは勝手が違うなと思われた事は?
都倉:ミュージカルというのは、全ての決定権がディレクターにあるんですよ。それで、ディレクターは、無慈悲にもバッサバッサとシーンをカットしちゃうわけ。上演時間の調整だったり、全体の構成を考えてシーンをカットするわけで、そこに音楽的な観点はないから、我々作曲家からするとね、いちばん重要な所が抜けちゃって、頭と尻尾しか残らないというような曲も出てきちゃうんですよ。特に、ソング・スルーと言って、セリフがないシーンね。そういう場面はカットされやすいから、スコアが中途半端になっちゃう。あ~いいメロディなのになぁと、非常に残念に思う事も多かったですね。

──ミュージカル曲を書かれるようになって、楽曲づくりに対する考え方や捉え方に変化はありましたか?
都倉:音だけで勝負したい、言葉を伴わずに“音”が語りかける力というのがどれくらいあるのかを試したいと言っておきながら、ちょっと矛盾してしまうんだけれども、ミュージカルをやり始めて20年経って、やっぱり、言葉が持つパワーというものも改めて実感しているんですね。
ミュージカル曲の場合は、大半は詞が先です。詞には、言葉を作る人のインテリジェンスというものが表れるんですよね。僕が手がけてきたものは大半が英語詞ですけど、ウィットとかユーモアのセンスにしびれちゃう事があるんですよ。例えば、「お茶をくださいね」という場面で、ウエイターとのちょっとしたやりとりの中でね、どうしてこんなに素敵な言いまわしができるの?と、うっとりするようなフレーズが出てきたりするんですね。
──言葉の持つインテリジェンスで生まれるメロディも変わってくる?
都倉:ええ、そういう事はありますよ。もちろん、どんな詞であろうと、音楽は音楽としてその世界観を表現していくわけですけど、見事に韻を踏んでいる詞であれば、そのリズムの美しさを生かしたいと思うし、素敵でエレガントなセリフであれば、それに見合ったメロディをつけなくちゃと思うし。素晴らしい言葉に出会った時はね、“おっ、ここは言葉に主役の座を譲った方がいいぞ”と思うんですよ。
そんな風に、その作家の背景まで感じられるような詞で生まれるミュージカルというのは、自然と音楽も奥深いオーケストレーションになっていく。そうやって、言葉と音楽がお互いを高め合って、芸が深くなっていくんですよね。
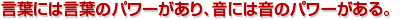
 ──ミュージカルを通して、詞の大切さを改めてお感じになったと? ──ミュージカルを通して、詞の大切さを改めてお感じになったと?
都倉:その通りですね。僕が昔作った曲には申し訳ないと思うんだけれども、僕が“詞”を本当に大切だなと思えるようになったのは、ミュージカルを始めてからですね。詞の深さというものを、作曲家として追求したいと、本当にそう思い始めたのは、ずいぶん経ってからです。そう気づいた時、僕もこれでやっと大人になったと思いましたよ(笑)。
阿久さんが亡くなって、たぶん、やり残した事がたくさんあってとても無念だったろうなと思いますが、一方でね、まだまだ誰にも引き出されていない言葉の力というのが、たくさんあるはずだとも思うんですよ。これからの音楽シーンで、言葉の持つパワーはもっともっと引き出せると思いますね。
──言葉の持つ力というお話を伺ったうえで、『フェリシティー(至福の時)』を聴くと、また、違った面白さを感じられるような気がしてきました。
都倉:そうかもしれないですね。歌には、ドラマがあり、メッセージがあり、それを伝えるのは“詞”という言葉ですね。だから、僕は、詞というのは“文学”だと思うし、本当に大切なものだと思います。でも、先ほど、右脳・左脳なんていう話もしましたが、言葉は、理解して感じるものですが、音というのは、理屈抜きに体が感じるものでしょう。音でしか感じられないもの、サウンドのアンサンブルの心地良さや楽しさ。僕は、音楽家として、そこをもっともっと深く追求したいんと思うんです。だから、聴きなれたメロディーを、この『フェリシティー(至福の時)』のアレンジで聴いていただいて、音の表現力、インストゥルメンタルの楽しさというものが伝わったら、とてもうれしく思います。

 |